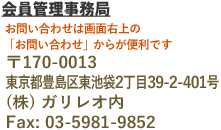理事長挨拶
 2023年1月より理事長を拝命しております、淑徳大学看護栄養学部の小川純子です。
2023年1月より理事長を拝命しております、淑徳大学看護栄養学部の小川純子です。
2020年1月より感染拡大し3年以上もの期間、人々に生活の制限を課してきた新型コロナウィルス感染症が、この5月に「5類」に移行されました。会員の皆様におきましては、今なおご苦労が多い日々を送られていることと存じます。このような中で、学会活動にご協力頂き、心より感謝申し上げます。
2003年2月8日に小児がん看護研究会として設立した本学会は、2023年2月で丸20年になりました。小児がん看護学会の歴史は、私の教員としての歴史でもあります。教員1年目であった私は、「小児がん看護に関する集まりあるので参加したらどうか」と言われ、東邦大学医療短期大学(現 東邦大学看護学部)に参りました。その場が、小児がん看護研究会の設立準備会でした。初代理事長 梶山祥子先生の元、小児がん看護に精通した諸先輩方と一緒に発起人の一人に混ぜて頂き、広報担当の役員となりました。依頼20年間、小児がん看護研究会、小児がん看護学会の理事として、本会の活動に関わらせていただいてきました。発起人18名で始めた会は、小児がん看護研究会から小児がん看護学会、そして現在の「非営利活動法人小児がん看護学会」へと成長し、会員数は700名を越えています。
小児がんに関する国の動きとしては、2023年3月末に閣議決定された「第4期がん対策基本計画」では、『「誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての国民とがんの克服を目指す」が掲げられました。小児・AYA世代の患者の医療や療養環境についても明文化されており、看護師にもとめられる役割がますます大きくなっていると感じております。また、2013年から選定された小児がん拠点病院で治療を受けている子ども達は全体の4割にすぎず、半数以上の子ども達が、拠点病院以外の様々な病院で治療を受けていることが明らかになっています。小児・AYA世代の小児がんの患者さん達が、どこにいても質の高いケアを受けられるように、施設を越えての情報交換や発信など課題や問題を共有し、検討を重ねていく必要性を感じています。また、学会として、小児がん看護におけるエビデンスの構築、小児がん看護の教育活動の発展に貢献できるよう、活動して参ります。
2021年度からは、より多くの会員の方の意見を学会活動に反映できるように、選挙制度を整え、会員選挙で評議員を選出し、今期は、評議員による初めての選挙で役員を選出しました。今後は、4年ごとに評議員選挙、2年ごとに役員選挙が行われ、2年ごとに運営組織が変わることを鑑み、初代理事長梶山祥子先生、2代目内田雅代理事長、3代目上別府圭子理事長が、大切にしてきたことを守りながら、スムーズな組織交代が出来る仕組みを作るのも、今期の理事会に課せられた役割のひとつと考えております。
会員の皆様にとって有益な事業をお届けできるよう、役員と共に小児がん患者・経験者とその家族に対する看護ケアの質の向上を目指して一生懸命取り組んで参ります。
今後とも、学会への積極的参加をよろしくお願い致します。
2023年7月
日本小児がん看護学会
理事長 小川 純子